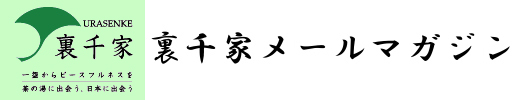 |
| 第26号(平成25年9月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『50年』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:無限斎碩叟宗室居士五十回忌法要にて) |
|
こんにちは! 朝晩が大分涼しくなってきました。そろそろタオルケットから布団に変えようか悩みの種です。 さて、先週は無限斎碩叟宗室居士の五十回忌に続き少庵宗淳居士の四百年忌を執り行いました。 四百年忌は三千家合同での供養であり、三千家の親族が揃う貴重な機会でもありました。 最後に全員で写真を撮るのが恒例だそうで、前回の少庵居士の法要は50年前。 次に少庵居士を偲んで皆で集まり写真を撮るのは50年後と思うと、なにか感慨深いものがありました。 50年後に向けて我々若手が茶道を紡いでいかなければならない。 気持ちも新たに9月も宜しくお願いいたします。 |
| ------------------------------------------------- 少庵の逸話その5 ------------------------------------------------- |
| 少庵の活動した時代は、美術史上で桃山時代といわれた力強く豪放な作品が生み出された時代でした。茶の湯道具も同様ですが、利休に関わりをもつ茶道具のみが、物静かで内に秘めるところがあったと評価されています。少庵の茶道具は、「夜桜棗」や「四方釜」(よほうがま)などのように、さらに優美で気品あふれる趣を持っているものが多いようです。今回は少庵と茶道具にまつわる話をご紹介しましょう。 利休は、手に入れた瓢箪を花入にして、顔回(がんかい)という名を付けましたが、これを掛ける花釘を打つ場所で思案に暮れていました。そこで、試みに少庵に釘を打たせてみたところ、思いのほかよい場所に打ったので、利休は喜び、大いにほめたそうです。この話は『茶譜』(ちゃふ)にみえます。ちなみに顔回とは孔子の一番弟子顔淵(がんえん)のことです。花入顔回は現在、東京の永青(えいせい)文庫に所蔵されています。 またある時、利休が竹の蓋置の節ありと、節なしの二種類を切って、二人の息子に示しました。道安は節ありを選び取り、少庵は節なしを選びました。すると利休は、「節なしの蓋置のほうが良いものだ」と、少庵に軍配をあげたということです。この蓋置は宗旦に伝えられ、宗旦から加賀の前田利長公に献上され、大切に扱われたそうです。『江岑夏書』(こうしんげがき)に載る話です。 |
| ------------------------------------------------- 資料館学芸員出張所 ------------------------------------------------- |
 |
| 田口釜 銘桜川 少庵所持 西村道仁作 |
| 少庵の好みを代表する釜です。田口釜とは口造りの周囲に肩より低い溝のある釜のことをいい、水がたまると田の面のようになることからこの名称がつけられるようになったとされます。替蓋として唐銅蓋が二枚添っています。 本作は宗旦所持の千家名物であり、通称「桜川釜」の本歌であります。添掛物として、天倫和尚筆の掛物が添っており、その内容から利休、少庵、宗旦と受け継がれたものであることがわかります。 |