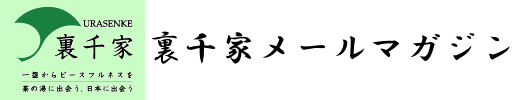 |
| 第24号(平成25年7月16日配信) |
| ------------------------------------------------- 『貴船の水まつり』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:貴船神社献茶式) |
|
こんにちは! 厳しい日差し、うだるような熱気。 女性にとっては色々と大変な夏がやってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか? 私は8日に毎年恒例の貴船神社献茶式を初めてご奉仕させていただきました。 亡くなりました父もこちらにご縁があり、親子二代に亘り奉仕させていただいたわけです。 貴船神社の献茶式はそれがメインなのではなく、水まつりの一環として執り行われているものです。 毎年神様への祈りが通じるのか、雨が降る、もしくは曇りといったまさに水まつりにふさわしい天気となります。 が、今年は私の晴れ男パワーが強かったのか生憎の快晴。 来年もご奉仕させていただけるのか、今から心配です。 |
| ------------------------------------------------- 少庵の逸話その3 ------------------------------------------------- |
| 少庵が亭主をつとめた茶会記は、5会分しか分かっていません。その数少ない茶会記から、今回はその茶風をうかがってみましょう。 天正10年(1582)正月26日、少庵は津田宗及を招いて茶会を開きました。初めての茶会です。場所は京都の大徳寺門前屋敷でした。そこで少庵は炉に自在鉤(じざいかぎ)を使い、霰釜(あられかま)を吊って宗及をもてなしました。使用した霰釜は利休の「霰百会釜」(あられひゃくえかま)と思われます。この茶会記は『天王寺屋会記』に収められています。 それから8年後の同18年8月7日、奈良の松屋久好が少庵のもとを訪れます。少庵は、利休参禅の師、古渓和尚の墨蹟(ぼくせき)を床に掛けて、久好を迎え入れます。これは利休の影響をうけたものでした。利休は古渓以外にも大燈国師など日本人禅僧の墨蹟を用いています。この茶会記は『松屋会記』にあります。 この二つの茶会は利休在世時のもので、少庵は利休の茶風に忠実だったと言われています。それでは利休没後はどうだったのでしょうか。 少庵は利休没後、慶長8年(1603)2月5日、同13年2月25日、同14年5月13日と茶会を催しています。いずれも奈良の松屋久好、久重など招いたものですが、これといった変化は見出せません。あくまでも利休の茶風に忠実だったようです。わずかな茶会記録からですが、利休の茶を伝える、これこそが少庵の使命だったのではないでしょうか。 |