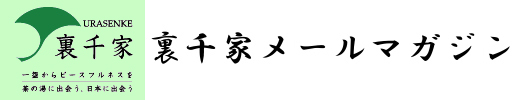 |
| 第22号(平成25年5月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『不思議な感覚』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| (写真:尾張大國霊神社献茶式本席にて) |
|
こんにちは! 先月末に愛知県の尾張大國霊神社、通称、国府宮神社にて初めて献茶を奉仕させていただきました。 応援に駆けつけてくれた容子伯母、母、水屋に控えてくれている業躰、また、参列された多くの同門の方々の熱い視線を受けながら、濃茶・薄茶二碗を御神殿に供え、初の大役を無事に済ますことができました。 今回の献茶式を通して、点前座は不思議な場所だということに改めて気づきました。 いざ点前畳を一歩踏み出すと、自分と神様の時間が始まります。 今まで色々な場所で点前をしてきましたが、本当の意味で無心になれたのは初めてです。 まだまだ修行中の身ですが、「これが“無”なのかな」と感じることができました。 今まで経験したことのない不思議な感覚に浸れた、そんな献茶式でした。 今月は大宮八幡宮、大宮氷川神社でも献茶を奉仕させていただきました。 この不思議な感覚を大切に、これからも点前座に向かいます。 |
| ------------------------------------------------- 少庵の逸話その1 ------------------------------------------------- |
| 先号まで、9月7日に50回忌を迎えられる第14代無限斎宗匠の好物をご紹介してきました。今号からは、同日400回忌を迎えられる、第2代少庵宗淳(しょうあんそうじゅん)居士の逸話を通して、その茶風と人となりをご紹介したいと思います。居士が千家を再興し、宗旦という後継者を遺してくれたからこそ、今の三千家があるわけですから、とても重要な人物と言えましょう。 少庵の父母について、『四座役者目録』(よざやくしゃもくろく)には、父は能楽の小鼓(こつづみ)打ちだった宮王(みやおう)三郎三入(さんにゅう)という人で、母は三入が亡くなったのち、少庵を連れて千利休のもとに嫁(とつ)いだとあります。また『茶道四祖伝書』(ちゃどうしそでんしょ)にも同様のことが書かれていますが、さらに母の名を宗音(恩)だとしています。 『敝帚記補』(へいそうきほ)では、少庵は名を宗淳といい、利休の第二番目の子であり、妻は利休の娘だったとあります。 これらの話を総合すると、父は宮王三郎三入で、後に母宗恩が利休に嫁いだため、一緒に千家に入ります。しかし利休には長男道安がおり、二男とされました。なお少庵の妻は利休の娘でした。つまり宗旦は利休の孫なのです。 以後、茶人千 少庵の歩みが始まります。 |