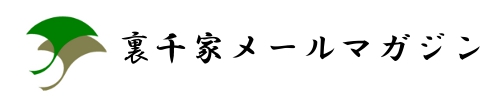 |
| 第20号(平成25年3月15日配信) |
 |
| ------------------------------------------------- 『季節の移ろい』 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
|
こんにちは! 京都は随分と暖かくなってまいりました。 読者の皆さんにはもう梅の花をご覧になった方もいらっしゃると思いますが、最近、今日庵内の遅咲きの梅がやっとほころび始めました。 お家元のプライベートの庭には、様々な花が植えられており、四季に彩りを添えてくれます。 体感温度、暦ではわからない季節感がそこにあります。 昔の人は自然の様子から季節を感じ取っていたのだなと感慨に耽る。 そんな三月です。 (写真:裏千家学園同窓会にて) |
| ------------------------------------------------- 無限斎碩叟好物:その5 ------------------------------------------------- |
 |
| 梅月棗(ばいげつなつめ) |
 |
| 同蓋表と身 |
 |
| 同蓋裏と身 |
| 梅月棗は、中国・北宋代の隠逸(いんいつ)詩人、林和靖(林逋)の漢詩「山園小梅」のなかの「疎影横斜水清浅 暗香浮動月黄昏」(そえいおうしゃ みずせいせん あんこうふどう つきこうこん)の二句をモチーフとして意匠されました。この詩は夜の梅を詠んだ幻想的な詩として、古来より人々に受け入れられてきました。溜塗折撓(ためぬり おりため)の大棗に、梅の木と月が黒漆と銀蒔絵で描かれ、月にかかった枝の一部のみ金蒔絵となっています。 蓋裏には朱漆(しゅうるし)で無限斎の花押が直書されています。無限斎好みの棗の中でも随一と評価されているものです。 ちなみに溜塗とは、透き漆(すきうるし)という透明な漆を塗って仕上げる技法です。折撓は、桧や杉の片木板(へぎいた)を折り曲げて器を成形するので、轆轤(ろくろ)引きされたものとは違い、ざんぐりとした風合いが特徴です。 十四代飛来一閑と十一代中村宗哲の合作。 高さ7.8 径7.5 底径3.8 単位はいずれもcm 茶道資料館蔵 |
| ------------------------------------------------- 海外の茶の湯:湖畔の親睦茶会(スイス) ------------------------------------------------- |
| スイス・淡交会チューリッヒ協会 宮西加織 会長 |
| チューリッヒ協会では会員の交流と稽古の実践の場として毎年親睦茶会を企画しています。昨年は、6月にチューリッヒ湖畔のボートクラブを借り、芝生と木陰、そして桟橋にそれぞれ濃茶、茶箱、略盆の3席を設けました。参加者はくじ引きで席とともに主客の役割も交替しながら各席の趣向を楽しみました。 |
 |
| 木陰の茶席 |
| 濃茶席は、スイスではチーズや干し肉を盛るのによく使う板を芝生の上に敷いて道具を置き、まさしく芝点! 譜面台に色紙を掛けて床としました。腰を下ろすと草花が目の高さにあり、「花屏風が広がっているよう」と大変好評でした。 |
 |
| 芝生での濃茶席 |
| 中でも今回の目玉は桟橋のお席。真っ赤なパラソルを日よけとし船が通る度に揺れる非日常の茶席には、参加者から「楽しい」、「びっくりした」、「インスピレーションがわいてきた」との讃嘆の声が寄せられました。 |
  |
| 桟橋の茶席 |
| ------------------------------------------------- 資料館学芸員出張所 ------------------------------------------------- |
| 茶道資料館では、3月27日(水)〜5月26日(日)の期間、春季特別展として鎌倉時代より700年の長い歴史をもち、細川幽斎・三斎親子が名を馳せ、その後歴代当主が熊本藩54万石を治めた名門・細川家。永青文庫所蔵の細川家コレクションより、貴重な香木や雅な香道具を紹介いたします。また、香道具を初めて鑑賞する方にも親しみやすいように併設展を設けています。 今号では、その中でも特に香木「白菊」について、資料館学芸員が解説いたします。 |
 |
| 香木 銘「白菊」 |
| 必見!名香「白菊」来たる! 利休七哲の一人・細川三斎は、香道にも通じ、「一木三銘香」あるいは「一木四銘香」として有名な「白菊」を所有していた。一般には、一つの香木に銘は一つであるが、この香木には「初音」「白菊」「柴舟」、さらに献上香に「藤袴」という銘が付けられたという。この「白菊」は、明治の文豪、森鴎外の『興津弥五右衛門の遺書』に登場する香木のモデルだと言われている。 |