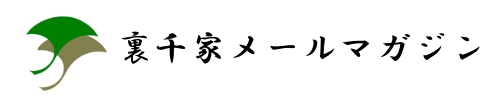 |
| 第15号(平成24年10月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 『秋を探して・・・』伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
 |
| こんにちは! 10月に入り朝晩は随分涼しくなってまいりましたが、皆さま体調はいかがでしょうか? 秋の行楽シーズンということもあり、週末の京都は観光客で賑わっております。 お出かけするには本当に過ごしやすい季節となりました。 宗家でも、この時期は行事等で各地に出張させていただく機会が増えます。 会員の皆さまとの触れ合いを楽しみつつ、その地方ならではの秋を探せる。 そんな素敵な10月です。 (写真:三河支部創立40周年記念行事薄茶席にて) |
| ------------------------------------------------- 茶人の逸話その7: 古田織部 ------------------------------------------------- |
| 古田織部(1544~1615)は、美濃出身の武将で、はじめ織田信長に、その没後は豊臣秀吉に仕えました。師の千 利休亡きあと天下一と称され、織部の茶風は大いにもてはやされましたが、大坂夏の陣の後、徳川幕府から豊臣氏へ内通した疑いをかけられ自害しました。 織部の茶風の一端を示すのが、神谷宗湛らを招いた茶会で「セト茶碗、ヒツミ候也、ヘウケモノ也」と記されたように、変形したゆがみ茶碗を使用したことでしょう。「ひょうげもの」ひょうきん者と評されたこの茶碗は、現在伝えられている黒織部沓茶碗と同様なものと考えられています。 |
 |
| 黒織部沓茶碗 |
| いくつかある織部の逸話のなかでも、利休が織部の作意に感服し、それを自らの茶に取り入れた話をご紹介しましょう。織部が利休を招いたある茶会でのことです。利休が席入りをしますと、織部は籠の花入を使っていながら薄板を敷いていませんでした。当時はまだ胡銅や青磁などの唐物と同じように籠の花入にも薄板を用いるのが常識でしたから、利休は織部の常識破りのくだけた作意に驚いて、「私も籠の花入に薄板を敷くのはおかしいと思いながら、今まで用いてきました。しかしあなたの作意は大変おもしろい。このことに関して私はあなたのお弟子になりましょう」、といって弟子の織部を誉め、これ以後、利休は籠の花入を使用するときは薄板を敷かず、じかに置くようになりました。 古田織部の出身地である岐阜県本巣市の「道の駅 織部の里もとす」には、「織部展示館」が設けられ、織部について紹介がされています。 |
 |
| 織部展示館内部 |
 |
| 古田織部像 |
| ------------------------------------------------- 茶道資料館学芸員出張所 ------------------------------------------------- |
| 今号の「学芸員出張所」は現在開催中の秋季特別展「-茶会記にみる茶道具-姫路藩主 酒井宗雅の茶と交遊」より酒井宗雅本人の手による赤楽茶碗について解説します。 |
| この度の展覧会では、江戸時代中期の大名茶人の酒井宗雅が残した茶会記『逾好日記』と日次記『玄武日記』に記された茶会や茶道具、茶の湯を通した交遊等を取り上げ、宗雅の茶の湯に対する思いにも触れてみたいと思います。皆さまのご来館をお待ちしております。 |
 |
| 赤楽茶碗 酒井宗雅作 (個人蔵) |
| 高10.3、口径11.2、胴径12.7、高台径5.4×6.0 (㎝) 播州姫路藩主・酒井宗雅(1755~1790)は、江戸中期を代表する大名茶人で、酒井抱一の兄、松平不昧の高弟として知られている。本作品は、宗雅手造の茶碗として現存が確認できる、唯一の茶碗である。口縁から胴部に掛けて淡い緑釉が掛かった赤茶碗で、高台周辺に残された力強く大胆なヘラ目からは、風雅を愛する宗雅像とは異なる、武家としての豪快さも窺われる。胴部には宗雅の庵号である「弌得」の丸枠印が捺されている。 当展覧会では、この他にも酒井宗雅の日記に因った道具を展示しております。 皆様のご来館をお待ちしています。 ※茶道資料館は10月29日(月)~31日(水)の間展示替えの為、休館します。開催は11月25日(日)まで |