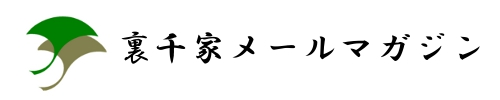 |
| 第7号(平成24年2月15日配信) |
| ------------------------------------------------- 「ホッと一息」 伊住公一朗 ------------------------------------------------- |
| こんにちは! 1月の初釜式にご来庵くださった皆様、有難うございました。 また、震災に遭われた東北の皆様方のお顔も拝見できてホッとしております。 足早に過ぎて行った1月も終わり、宗家内も少し穏やかとなりました。唐突ながら私の今年の目標!!! その1、チャレンジの1年 その2、全国の皆様との交流をより深める その3、ファッションに気を使う 皆さんの今年の目標はなんですか? 目標=テーマをもって1年を有意義に過ごしましょう。 (写真:執務室にて) |
 |
| ------------------------------------------------- 茶道資料館新春展 筒井紘一今日庵文庫長インタビュー 「茶の湯の趣向」 ------------------------------------------------- |
 お茶の趣向というのは本来、自分の持つあらゆる知識を使った表現をお客様に見せることだと思います。そういう意味では新春の茶会というのはなかなかに難しいものです。新年それ自体が趣向で、季節感と干支でおもてなしということになってしまう。季節感も茶の湯の楽しみではありますが、それだけだと限界があって、待合に入った時に席の全てが分かってしまい、席に入った後の驚きがありません。新年に限らず、どうすれば亭主が趣向を凝らした一会を持てるのでしょうか。これを山上宗二は文学と和歌だといったのですね。 お茶の趣向というのは本来、自分の持つあらゆる知識を使った表現をお客様に見せることだと思います。そういう意味では新春の茶会というのはなかなかに難しいものです。新年それ自体が趣向で、季節感と干支でおもてなしということになってしまう。季節感も茶の湯の楽しみではありますが、それだけだと限界があって、待合に入った時に席の全てが分かってしまい、席に入った後の驚きがありません。新年に限らず、どうすれば亭主が趣向を凝らした一会を持てるのでしょうか。これを山上宗二は文学と和歌だといったのですね。宗二は「茶の湯者は無能なるが一能なり」といっています。これは茶人は茶の湯に専念するべきで、人生のうちであれもこれもと学んでも身につかないといった意味です。そういった後で宗二は、しかしと続け、例外として文学と和歌を挙げています。源氏物語、伊勢物語、古今和歌集、万葉集といったものを読まずにどんな趣向ができますか、と宗二はいっています。 これをよくよく考えると、文学と和歌に限らず茶人は能や狂言、歌舞伎あるいは中国の古典の知識を沢山取り入れておくことが肝要になるのではないでしょうか。そうした知識を駆使することで、茶の湯がとても面白くなります。例えば、九月に待合に入ったら枕が置いてある。客もなんだろうな、と考えるんですね。旅枕の時季ではないし、一炊の夢かもしれない。そして茶席に入って、菊があり、着せ綿があり、お酒がありで菊慈童の枕という意味が分かります。席の進行の中でひとつずつ出てくるわけですから、どこで分かるか。亭主と客の頭の中で一種の戦いとなるわけです。そこが面白いのですね。それなのに、客が今日の枕は何でございますか、なんて聞いたら亭主はガクッとくるのではないでしょうか。 つづきはこちら:http://www.urasenke.or.jp/image/magazine/120215t2.html |
| ------------------------------------------------- 【メルマガ一碗】福島支部 加藤宗美 ------------------------------------------------- |
| 本文:http://www.urasenke.or.jp/image/magazine/120215t3.html |