| 初心者のための 茶道教室 2010年4月教室 |
裏千家(財)今日庵 フリーダイヤル(9:00〜18:00) 0120−31−1166  Email はこちらから Email はこちらから |
ホテルコンコルド浜松教室 |
| 許状授与式 | |
| 9月15日(水)、淡交会浜松支部 岡本宗弘幹事長により許状授与式が執り行われました。 岡本幹事長は、茶道の在り方や歴史についての話を交えながら、受講生の今後の修道を激励しました。 その後の茶会では、岡本幹事長をお客に半年間の成果を披露し、お世話になった先生方や共に学んだ仲間と笑顔でのお別れとなりました。 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 一人ずつに許状を手渡す岡本幹事長(左) | ||
 |
 |
| 22回のレッスン最後の一服は、感謝の気持ちで点てました | |
 |
 |
 |
| 講師より この度は、大宗匠様、お家元様にはこのような機会を与えてくだ さり、ありがとうございました。先生を亡くして落ち込んでいる私に 手を差しのべて下さった岡本幹事長先生、開講まもなくして膝の 具合いが悪く椅子を使っての指導に、優しく接して下さった講師 のM先生、いつも励ましの声かけをくれた生徒の皆様、本当にあ りがとうございました。 この半年間は、私にとって茶道の真髄に触れた思いで、有意義 で実の有る期間となりました。この経験を今後に活かしていきた いと思います。 (講師 K) |
| レッスン風景10 | |
| 8月の稽古風景が届きました。 8月4日(水)洗い茶巾や葉蓋などを稽古。 |
 |
 |
 |
| 洗い茶巾 | 平茶碗は点てにくいです | 葉蓋 |
| 8月18日(水)、平花月にチャレンジ。 | |
 |
 |
| 「月」「花」は名乗ります | 替え札を請求 |
| 8月25日(水)、濃茶体験。 | |
 |
 |
| 柄杓を引いたら、主客総礼 | 先生の点前を皆真剣に見つめます |
 |
 |
| 茶碗を次客へ手渡しで送ります | 初めて聞くお道具の問答も体験 |
| レッスン風景9 | |
| 7月28日(水)の稽古風景が届きました。 「葉蓋」点前に皆、一生懸命です。 | |
 |
 |
 | |
| レッスン風景8 | |
| 1週間のお盆休みも明け、お稽古再開となる7月21日(水)の稽古風景が届きました。 |
 |
 |
 |
| 涼しげな掛物にガラスの茶碗など、涼を感じるお道具を使っての稽古 | ||
 |
 |
| 段々と点前も客の所作も慣れてきました | |
| レッスン風景7 | |
| 6月30日(水)、段々と点前に慣れてきたこともあり、細かな所作を確認しながらの稽古となりました。 | |
 |
 |
   | |
| 指先や姿勢、肘の形など、気をつけながら稽古できるようになりました | |
| 7月7日(水)は、洗い茶巾にチャレンジ。茶杓の銘には七夕らしい銘が聞かれました。 | |
 |
 |
| 「櫂先を下げてね」 | 柄杓の扱い |
 |
 |
| 「お菓子をどうぞ」 | 洗い茶巾をするための割稽古 |
| レッスン風景6 | |
| 6月16・23日(水)、3ヶ月が経ちました。薄茶棚点前が始まりました。 |
 |
 |
 |
| 宗旦好丸卓 | 玄々斎好更好棚 | 利休好桂籠 |
 |
 |
| 一つ一つを丁寧に指導 | |
 |
 |
| 「この平茶碗、可愛い〜」 | 切柄杓、綺麗に決まった! |
| レッスン風景5 | |
| 6月9日(水)、稽古も9回目となり、棗と茶杓の拝見の所作に戸惑うこともありますが、お菓子や器など、点前以外のものに興味が出てくるようになり、和やかにゆっくりとした2時間が過ぎていきます。 | |
   | |
| 足の痺れも忘れるほど真剣に稽古しています | |
 | |
 |
 |
| 楽しくお稽古しています | |
| レッスン風景4 | |
| 5月19・26日(水)、薄茶点前の稽古風景が届きました。 受講生は皆、他の人の点前もしっかりと見て、予習復習をするように心がけているようです。 | |
 |
 |
| 床の間の掛物・お花を拝見 | お菓子をどうぞ |
 |
 |
| 水指を釻付にあわせて置いて・・・ | 棗・茶杓を清めます |
 |
 |
 |
| 蓋を八時、十時のところを持ってね | 切柄杓 | 茶碗の拝見 |
| レッスン風景3 | |
| 5月12日(水)の稽古風景が届きました。 薄茶点前では、柄杓の扱いが難しくなかなか思うように指が動かず、苦労しています。 | |
 |
 |
| 柄杓の扱いに一苦労です | |
 |
 |
| 柄杓を落とさないように建水を運びます | 2ヶ所でお稽古 |
| 受講生より レッスンも5回目となり、笑顔も多くなってきました。毎回 頂くお菓子は大変美味しく、楽しみです。広間ではお茶を自 席まで運び、お茶も、分量や点て方によって毎回味の違いを 感じることが出来るようになってきました。 |
| レッスン風景2 | |
| 4月21日(水)、割稽古を兼ねての盆略点前。一つ一つの所作を思い出しながら一生懸命に取り組んでいます。 | |
 |
 |
 |
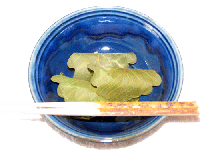 |
| 4月28日(水)は、和室ではなく、洋室で立礼式による盆略点前。いつもとは勝手が違う感じでしたが、足の痺れもなく集中して稽古ができました。 | |
 |
 |
| 割稽古で習った所作を一つずつ確認しながら盆略点前 | |
| 開講 | |
| 4月7日(水曜日)、桜が満開の浜松城公園を眼下に望むホテルコンコルド浜松教室が淡交会浜松支部 岡本宗弘幹事長挨拶にて開講しました。 まずは、懐中道具の名称・使い方などを一つずつ説明。襖の開け方、席入りの仕方からレッスンが始まりました。翌週14日は、帛紗捌き、茶巾の扱いなど割稽古を熱心に取り組んでいました。 |
 |
 |
 |
| 持ち物の説明から | 席入り |
 |
 |
| 襖の開け方・閉め方、席入り | |
 |
 |
| お菓子を運び、一礼 | 割稽古 |
 |
 |
 |
| 岡本幹事長(左から3番目)と講師・受講生 | ||