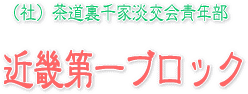 |  |
御膝元、これが私たち近畿第一ブロックの代名詞となっています。 京都・近江・大和・但馬・丹後と、日本の中でも古い歴史を有するブロックです。ゆえに寺社を多くかかえ有名なお茶室が沢山あります。又、青年部メンバーも、茶道具・庭・茶室・料理・菓子と、茶道との関わりあいの深い仕事にたずさわっている方が多いようです。皆様、何かございましたら近畿第一ブロックを思い出していろいろ御用命下さい。
|
近畿第一ブロック 26青年部
|
|
■ リレー茶会日程 ■
リレー茶会は随時アップします。ブラウザの「更新」ボタンをクリックして最新状態でご覧下さい。
| 日 程 | 場 所 | 時間 | 茶券 | 担 当 |
| 8月24日(日) | 北陸信越ブロックより引継ぎ | 北陸信越ブロック 近畿第一ブロック | ||
| 8月25日(月) | 守山市民ホール (守山市) | 17:00〜21:00 | 正会員 500円 一般 1000円 | 滋賀支部水の郷青年部 |
| 8月26日(火) | 菓匠 菊屋 菊寿亭 (大和郡山市) | 17:00〜21:00 | 無料 | 奈良支部青年部連絡会 |
| 8月27日(水) | 池坊学園 (京都市) | 19:00〜20:00 | 500円 | 京都東支部 洛東・東山青年部 |
| 8月28日(木) | みやづ歴史の館 大会議室3F (宮津市) | 16:00〜19:00 | 500円 | 宮津支部宮津青年部 |
| 8月29日(金) | 舞鶴市西市民プラザ (舞鶴市) | 17:00〜21:00 | 500円 | 両丹支部 舞鶴・丹の国青年部 |
| 8月30日(土) | 日高町民センター (城崎郡日高町) | 13:30〜17:00 | 無料 | 但馬支部青年部連絡会 |
| 8月31日(日) | 上七軒歌舞練場 (京都市) | 10:00〜15:00 | 1000円 | 近畿第一ブロック |
| 9月 1日(月) | 池坊学園 (京都市) | 11:00〜16:00 | 1000円 | 京都西支部 洛西・西山青年部 |
| 9月 2日(火) | もち料理北村 京都文化博物館店 | 16:00〜21:00 | 3500円 | 京都南支部 洛南・山城青年部 |
| 9月 3日(水) | 新風館 | 16:00〜20:30 | 無料 | 京都北支部 青年部連絡会 |
| 9月 4日(木) | 京都宝ケ池プリンスホテル | 17:00〜 | 無料 | 近畿第一ブロック 近畿第二ブロック合同 |
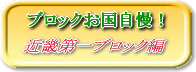
近畿第一ブロック内のあんなものこんなもの、なんでも紹介しちゃいます!
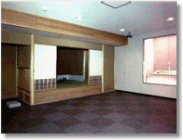 【茶道資料館】(京都) 皆さんご存知、京都裏千家センター内にあります茶道資料館。十五代 鵬雲斎家元の発案で昭和54年に設立。茶道に関する資料収集と調査研究を行い、あわせて展示事業を実施されています。今日庵文庫も併設されています。 | ||
| 名勝依水園は屈指の池泉回遊式庭園。特に後園は、若草山・春曰奥山・御蓋山を遠景に、借景に東大寺南大門の甍という大らかな天平時代の眺望を楽しめる。ユニークな外観の寧楽美術館は、設立者中村準策が収集した東洋の古美術を中心に所蔵品を展示している。 | 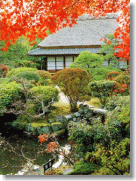 | |
 彦根城博物館の中央に建つ能舞台は、江戸時代の表御殿の中で現存する唯一の建物です。当博物館では、この能舞台を活用する「動的な博物館」として、能・狂言をはじめとする伝統芸能の上演や、コンサートなどの催しを行っています。 | ||
二畳隅炉の待庵は当時と同じ場所にほとんどそのまま現存する最古の茶室建造物で利休の遺構としては唯一のものです。内部は掛け込み天井と棹縁天井の組み合わせ、床の間の隅や天井を塗りまわした室床の構造から、二畳のわりには広く感じられ、連子窓、下地窓の配置、すさを出した壁の塗り方、やや広い躙口(にじりぐち)隅炉などと共に利休の非凡さがうかがわれます。 | 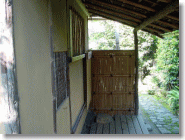 | |
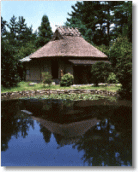 明治25年(1892)奈良国立博物館の中庭に移設された八窓庵は、もと興福寺の大乗院庭内にあった茶室で、含翠亭ともいい江戸時代中期に建てられた。古田織部好みと伝えられる多窓式茶室として有名である | ||
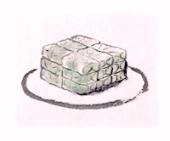 後亀山天皇の時代、土地の人々が天皇の孫、空因親王に鯖寿司を献納しました。親王はことのほか賞味され臣下に分け与えようとされましたが、適当な器がなく、とっさに柿の葉に寿司をのせ下賜されたのが柿の葉寿司の始まりだと伝えられています。 | ||
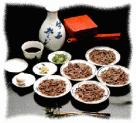 兵庫県の北部の但馬地方に位置する城下町いずし。その昔5万8千石の城下町として栄え、いま現在、町内に49軒もの蕎麦屋が並ぶ街となっております。その名産が、出石皿そばです。 | ||
京の米櫃と言われた肥沃な土地に稔る近江米。豊かに湧き出る鈴鹿山麓から通ずる伏流水。「比叡おろし」と呼ばれる近江盆地の寒気。そこに良質のお酒が生まれました。会員おすすめは、香の泉(竹内酒造)と喜楽長(喜多酒造) | ||
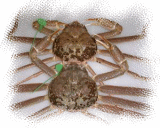 丹後を代表する松葉蟹の中でも一際美味とされるのが間人港に水揚げされる間人蟹です。間人港は魚場に一番近く日帰りで漁が出来るため、より新鮮な状態で食すことが出来ます。 | ||
 京都市伏見区にある御香宮神社で平安時代から湧き出る香り高いお水。軟水で名水百選を選ぶ基準ともなりました。女酒と呼ばれる伏見のお酒に伏見の水が起因したことが伺われます。 | ||
■全国大会トップページへ戻ります ■ブロック紹介トップページへ戻ります
■このページのトップへ戻ります■
【制作責任】第13回全国大会実行委員会(IT・リレー茶会部会)