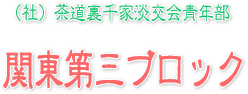 | 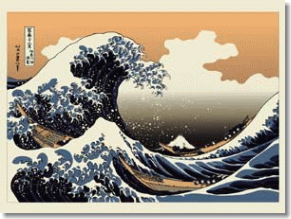 |
これっきり、もう・・そう言えば、横須賀はペリーが来港して150周年なんですよ! あなたと越えたい・・そう言えば、研ナオコさんて、伊豆湯ヶ島出身なんですよ! 行って、行ってしまった・・そう言えば、横浜で役員会やるたびに終電に乗り遅れるんです! 江の島が見えてきた・・そう言えば、江の島の灯台が今年新しくなったんですよ! 見つめ合うと(乗ってけ、乗ってけ・・OB用)・・そう言えば、関東第三ブロックリレー茶会の合言葉は「波をつくろう!波に乗れ!」 大きな波をつくりますよ~!七日間、いつでもどこでもウエルカム!是非、遊びに来て下さい!
|
関東第三ブロック 16青年部
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ リレー茶会日程 ■
リレー茶会は随時アップします。ブラウザの「更新」ボタンをクリックして最新状態でご覧下さい。
| 日 程 | 場 所 | 時間 | 茶券 | 担 当 |
| 8月 3日(日) | 関東第一ブロックより引継式 | 関東第一ブロック 関東第三ブロック | ||
| 8月 4日(月) | ヴェルクよこすか 横須賀市立勤労福祉会館 (横須賀市) | 13:00~17:00 | 1000円 | 横須賀支部 横須賀青年部 |
| 8月 5日(火) | 松籟庵 (茅ヶ崎市) | 11:00~14:00 | 1500円 | 湘南支部 湘南こゆるぎ青年部 |
| 8月 6日(水) | 小田原市民会館 (小田原市) | 17:00~20:00 | 500円 | 小田原支部青年部連絡会 |
| 8月 7日(木) | 鎌倉ギャラリー (鎌倉市) | 17:00~20:30 | 無料 | 鎌倉支部鎌倉第一・ 鎌倉第二・鎌倉第三青年部 |
| 8月 8日(金) | 川崎市役所 第3庁舎 (川崎市) | 15:00~19:00 | 無料 | 川崎支部 琢磨・橘樹青年部 |
| 8月 9日(土) | 三島商工会議所会館 (三島市) | 10:30~15:00 | 1500円 | 熱海支部熱海青年部 東静支部狩野川青年部 |
| 8月10日(日) | A:ロイヤルパークホテル65F「開光庵」 B:パシフィコ横浜会議センター2F C:山手西洋館「ベーリックホール」 (横浜市) | 10:00~16:00 | A:5500円 B:無料 C:無料 | 相模支部沙羅青年部 横浜支部港都・洒凡・ はまなみ・ぴあ青年部 |
| 8月10日(日) | 東海ブロックへ引継式 | 関東第三ブロック 東海ブロック |
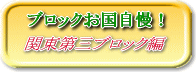
関東第三ブロック内のあんなものこんなもの、なんでも紹介しちゃいます!
| 茶室自慢 | ||
1919年(大正8年)に別荘として築かれた「起雲閣」。 熱海市のど真ん中に三千坪の庭園を有する名邸で、戦後、旅館となり、山本有三、志賀直哉、谷崎潤一郎、太宰治、三島由紀夫など文豪達にも愛されてきました。 現在は、市の所有で、展示室・和室は茶席としても貸し出していただけます。 |
県立大磯城山公園は、旧三井財閥別邸を利用した日本情緒あふれる公園です。 この公園は、中世の小磯城一帯を整備したもので、園内は温暖な気候に常緑樹が茂っています。園内にある茶室「城山庵」は、国宝の「如庵」にちなんで建てられたものでお茶事やお茶会に多く利用されています。 | |
原三溪によって明治39年に横浜につくられた広さ18万平方メートルの日本庭園で、四季折々の自然の景観の中に織田有楽斎の作と伝わる三畳台目の茶室「春草廬」等、京都や鎌倉から集められた数々の歴史的建造物が点在し、市民の憩いの場にもなっています。 |
小田原三茶人の一人である松永安右エ門が長年に渡り収集した美術品などを公開する目的に建てられた松永記念館の敷地内に移築された、野崎幻庵によって建てられた茶室。また、同敷地内には葉雨庵の寄付として建てられた小田原地方ではここでしか見られない樹木"天台烏薬"にちなんで名づけられた「烏薬亭」もある。 | |
美術館・博物館自慢 | ||
「みなとみらい」地区の近代的建築群にあり、三溪園創立者原三溪ゆかりの作家を重視しつつ、開港以来の洋画・日本画の流れを歴史的に捉え、国際港都ヨコハマに相応しい世界的な視野で展開されています。また市民が美術に親しむ場としてアトリエや情報ギャラリーがあり、様々な楽しみに溢れています。 | 急速に消滅しつつある古民家の保存を目的に、東日本各地から様々な民家を移築して作られた野外博物館です。民家の他にも水車小屋、船頭小屋、歌舞伎舞台など25件(うち18件は国・県の重文)の建物を見学できます。 毎年、川崎支部青年部ではこちらの民家で市民の方々にお呈茶をさせて頂いております。 | |
銘菓自慢 | ||
岡本太郎生誕の地という事から川崎市に建設された「岡本太郎美術館」の開園にちなみ発売されたお菓子。 その中身はまさに「夢」。市内の菓子匠夫々が「TAROの夢」さながら、思い思いの菓子を作りあげています。同じ名で異なるお菓子が販売されているユニークな川崎「銘菓」です。 | ||
創業1891年(明治24年)の和菓子店「新杵」の「西行まんじゅう」。 黒糖の皮と北海道産小豆のこしあんを使用した西行法師の傘をイメージしたお菓子です。 | ||
鎌倉土産数々あれど、力餅はいかがですか?「力餅家の力餅」あんこにくるまれた素朴な味 、でもオイシイ!!お店は極楽寺、紫陽花で有名な成就院の近く。 大仏殿御献茶式の青年部席のお菓子は必ず力餅です。 | ||
名所自慢 | ||
鎌倉のまちの特徴のひとつは、武家の信仰を集めた鶴岡八幡宮の参道である若宮大路が、800年余り経た今もなお、まちの都市軸として使われていることです。 これは京都や奈良と異なり類例を見ない貴重な歴史的遺産です。 | ||
日本を代表する港・横浜港は、2002年に大改修を終え新たに21世紀のクルーズ需要に応え得る客船ターミナルを擁した大桟橋を中心に、外海からの景観を重視し整備されたみなとみらい地区が広がり、その美しさは世界から感嘆の的になっています。 まさに日本の「海」の表玄関として胸を張って誇れる港と言えましょう。 | ||
正式には「金剛山平間寺」という真言宗のお寺ですが、弘法大師空海をご本尊に祀った川崎のお寺ということで「川崎大師」の名で親しまれ、年間を通して「災厄消除」等のご祈祷に多くの方がご参詣されます。 また、例年四月第二日曜には、お家元をお迎えして「ご供茶式とお茶会」が行なわれます。 | ||
名水自慢 | ||
沼津市と三島市にはさまれた清水町を流れる川で「21世紀に残したい日本の自然100選」や「名水100選」にも選ばれている。 富士山の恵みでもある湧水源は、大変珍しいことに国道直下にある。 | 平塚八景の一つ、松岩寺にある湧水は、1400年代末あるいは1500年代の初め頃から湧き続けており、枯れることなく約500年にわたって湧き出していることから不老水と命名され、大切にされています。 | |
路面電車を通すために彫られた「打越の切り通し」。湧水はその中腹あたりにあります、昔、港に来た外国船は質の良い飲料水の確保に苦労したそうです。 しかし横浜港で確保できる飲料水は大変美味しく、航海中でも腐りにくいと評判との事でした。この打越の霊水も外国船に有料で売っていたそうです。 | 相模支部の地元、座間は湧水が豊富であり特に神井戸湧水の近くには縄文中期の遺跡があることから、古来より人々の生活に欠かせないものだったことが伺いしれます。今も水道水の原水として活躍しています。 | |
お祭り自慢 | ||
平塚は昭和20年7月大空襲で壊滅的打撃を受け全市が焼野原と化してしまいました。昭和25年7月に復興祭りが開催され、その後仙台の七夕を模して毎年湘南平塚七夕まつりが行われるようになりました。 七夕祭りでは親先生と七夕見物に見えるお客様へ毎年お呈茶をしています。 | ||
リレー茶会が行われる頃、鎌倉はぼんぼりまつりでにぎわいます。黄昏時、鎌倉の著名人が絵や書を描いた400ほどの灯火が八幡宮の境内を幻想的に彩ります。今年で65回目を迎えるぼんぼりまつり、鎌倉の夏の風物詩です。 | ||
長く鎖国を続けてきた日本が開国をするきっかけとなったのぺりーの来航。そして、浦賀の近代的造船所・観音崎の様式灯台など現代の礎となった地です。 横須賀でリレー茶会が行われる頃、ペリー来航150周年を向かえるにあたり開催されるお祭りです。 | ||
事始自慢 | ||
日本に臨済禅と茶を伝えた栄西禅師は源実朝の帰依を受け、鎌倉に寿福寺を創建。その栄西が著したわが国最初の茶書である「喫茶養生記」。寿福寺本は「喫茶養生記」初治本の最も古い写本として有名です。 | 江戸末期から始まったと言っても良い横浜の短い歴史の中で、ハマっ子の自慢は「横浜が初めて」と言われるものです。鉄道、ガス灯、レストラン、クリーニング屋、牛乳屋、近代競馬場、ビール工場、アイスクリームなどがありますが、ここはなんと言っても日本料理の代表格として世界中にファンを持つ「スキヤキ」でしょう。このスキヤキも元を辿れば横浜の「牛鍋」です。 | |
■全国大会トップページへ戻ります ■ブロック紹介トップページへ戻ります
■このページのトップへ戻ります■
【制作責任】第13回全国大会実行委員会(IT・リレー茶会部会)